悪魔のトリル 一問一答
王子ホールマガジン Vol.32 より 来日のたびにコンチェルトやピアノとのデュオ、そして無伴奏でその魅力と実力を知らしめてきたネマニャ・ラドゥロヴィッチ。2011年3月には自身が結成した弦楽アンサンブル「悪魔のトリル」での演奏を披露し、熱烈なファン層をさらに広げました。この11月には再び同グループで来日、出来たてほやほやの新プログラムを王子ホールで披露してくれます。コンサートに先立ち、まずはこのグループについて、そしてプログラムについての一問一答(実際は「多答」ですが)をどうぞ。 |
ネマニャ・ラドゥロヴィチ(ヴァイオリン) ギヨーム・フォンタナローザ(ヴァイオリン) フレデリック・ドゥシュ(ヴァイオリン) ベルトラン・コス(ヴィオラ) アンヌ・ビラニェ(チェロ) スタニスラス・クシンスキ(コントラバス) |
Q まずは悪魔のトリル結成のきっかけをお話しいただけますか?
Q カルテット・イリコの活動について教えていただけますか?
フレデリック・ドゥシュ しかも僕たちも歌うんですよ! ベルトラン・コス(以下「ベルトラン」) 演劇的な効果を考えていちど試しにやってみたら、面白くなってどんどんその比重が大きくなってきました(笑)。 アンヌ 演出付きのコンサートというか、音楽だけにとどまらない表現を目指しています。コンサートではコメディー・フランセーズの総支配人であるミュリエル・マエットさんが演出をしてくれています。以前は2ヶ月間、楽器を持たずに俳優と同じトレーニングを受けたこともあります。はじめは楽器を持たないで表現しなければいけないからとても不安でした。それが2ヶ月後、今度は楽器を手にするのが不安に(笑)。とにかく舞台での身体表現のみに頼らなければならない状況を経験して、自分の肉体をどう使うかを意識するようになりました。
スタニスラス・クシンスキ(以下「スタニスラス」) 自分はパリ管で演奏したり、学校で教えたりもしているので、スケジュール調整に苦心しています。11月の来日時にはパリ管の公演も重なっていますので、そちらもぜひお越しください。 Q ネマニャさんにとって、このメンバーで演奏することの意義というか、喜びは? ネマニャ 悪魔のトリルのメンバーは演奏中それぞれ奔放に動いているので、その中に身を置くと、今まで考えられなかったような思い切った表現が湧いてくるときがあります。そうやって舞台上で自由な表現を続けていると、客席とのコミュニケーションという面でもどんどん変化が生まれる。オーケストラと共演しているときや、古典的な編成で演奏をする時とはまた違った、新鮮な刺激があります。このメンバーと演奏していると、出だしの音がひとつ鳴っただけで、いつも新しい風景が広がるんです。
ネマニャ 最初はフォンタナローザ先生が持っていたヴァイオリンとカルテット用の作品を漁るところから始めました。音楽史における旅ができるように、バロックに始まって古典派やロマン派、そして現代に続く流れを意識したプログラムを目指していたんですけれど、いろいろとやるうちに演奏曲が多くなりすぎてしまって、デビュープログラムは演奏だけで2時間かかってしまいました(笑)。そういうところからだんだんと練り上げていきました。ひとつ明確なのは、いわゆる『クロスオーバー』をやるつもりは全くないということ。あくまでもクラシックの作品に取り組みたい。 スタニスラス 何か奇をてらったことをしようという気もありません。クラシックの作品をどう聴かせることができるか、そして自分たちがどう表現したいか、そういった部分を出していきたい。
ネマニャ 独奏ヴァイオリンとピアノやオーケストラという編成の作品を演奏することが多いのですけど、マルク=オリヴィエ・デュパンさんの編曲の素晴らしいところは、独奏ヴァイオリン+αのための編曲であっても弦楽六重奏のために書かれた作品のように聴こえること。ソリストばかりを強調するのではなくて、全員がそれぞれの面白さを発揮できるようになっています。 Q 演出面でも工夫をされていますよね?
アンヌ スモークをたいてみたこともあります。でも加減がわからなかったものだからスモークを出しすぎて、むせちゃって大変でした。それ以来スモークはやっていません(笑)。 Q 最後に11月の王子ホール公演で披露する新プログラムについて一言お願いします。 ネマニャ これまで3、4年は同じプログラムを演奏してきたので、そろ アンヌ バッハの「シャコンヌ」の弦楽六重奏版は日本のツアーが初演になるかもしれませんね! ネマニャ 期待してください、まだ楽譜が出来上がっていないけど(笑)! (文・構成:柴田泰正 協力:アスペン 通訳:藤本優子 |
【公演情報】 |
| >>ページトップに戻る |

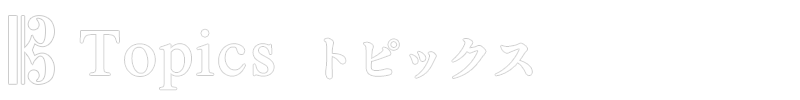
 悪魔のトリル(弦楽アンサンブル)
悪魔のトリル(弦楽アンサンブル) ネマニャ・ラドゥロヴィチ(以下「ネマニャ」) まずギヨームは僕の恩師であるパトリス・フォンタナローザ先生の息子さんで、かなり前から知っていました。コントラバスのスタニスラスはギヨームの友人で、残りの3人はギヨームの結成したカルテット・イリコのメンバーです。
ネマニャ・ラドゥロヴィチ(以下「ネマニャ」) まずギヨームは僕の恩師であるパトリス・フォンタナローザ先生の息子さんで、かなり前から知っていました。コントラバスのスタニスラスはギヨームの友人で、残りの3人はギヨームの結成したカルテット・イリコのメンバーです。
 Q スタニスラスさんの普段の活動は?
Q スタニスラスさんの普段の活動は? Q 悪魔のトリルのプログラミングについてお話しいただけますか?
Q 悪魔のトリルのプログラミングについてお話しいただけますか? ベルトラン このグループの特徴として、編曲ものをたくさん扱うという点があります。我々としては、ヴァイオリン属の楽器それぞれの個性を聴いてもらうというのも狙いのひとつです。
ベルトラン このグループの特徴として、編曲ものをたくさん扱うという点があります。我々としては、ヴァイオリン属の楽器それぞれの個性を聴いてもらうというのも狙いのひとつです。
 そろ新しいものをやりたいなと思っていたところなんです。今回はアレクサンドル・ベネト、アレクサンダー・セドラという2人の作曲家、それから先ほどもお話ししたデュパンさん。この3名の編曲が並ぶことになると思います。
そろ新しいものをやりたいなと思っていたところなんです。今回はアレクサンドル・ベネト、アレクサンダー・セドラという2人の作曲家、それから先ほどもお話ししたデュパンさん。この3名の編曲が並ぶことになると思います。