王子ホールマガジン 連載
|
王子ホールマガジン Vol.42 より |
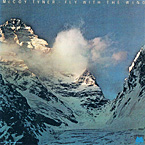
「フライ・ウィズ・ザ・ウインド」マッコイ・タイナー マッコイ・タイナー(p) ロン・カーター(b) ビリー・コブハム(ds) 1976年1月19~21日 |
「スタイリスト」という言葉は、一般にはタレントや俳優さんの衣裳、メイク、髪型をコーディネートする職業を指しますが、ジャズの世界ではちょっと違って、「ある演奏様式を開発・確立した人」に対して使われます。たとえばピアニストでいうと、バド・パウエルやビル・エヴァンス。もう少し新しい世代だとハービー・ハンコックやチック・コリア。彼らは、それまでの演奏スタイル――即興や和声の手法、リズム感覚等々――を統合し、かつ独自のアイディアを盛り込み、そこに分析・模倣が可能な「理論」を与えました。結果、彼らが創始したスタイルは広く流布することとなり、1つの流派を形成することになります。ジャズ・ファンはよく、「このピアニストはパウエル派だね」とか「エヴァンス派の新星」といういい方をしますが、これはそのピアニストがパウエルやエヴァンスのスタイルを継承している、影響を受けている、ということを意味するのです。
とはいえ、はじめてこのアルバムをきいた時の僕の印象は「えっ、これ本当にマッコイ?」というものでした。なぜなら、そこにきこえてきたのは、それまでの、どちらかというと暑苦しい彼とはずいぶん趣を異にする響き――朗々と鳴り響くストリングス、そこにかぶさり美しいメロディーを奏でる木管群、彩りを添えるハープ等々――だったからです。 |
著者紹介 藤本史昭/1961年生まれ。上智大学文学部国文学科卒。写真家・ジャズ評論家として活動。「ジャズ・ジャパン」誌ディスク・レビュアー。共著・執筆協力に『ブルーノートの名盤』(Gakken)、『菊地成孔セレクション~ロックとフォークのない20世紀』(Gakken)、『ジャズ名盤ベスト1000』(学研M文庫)などがある。王子ホールの舞台写真の多くは氏の撮影によるもの。 |
| >>ページトップに戻る |

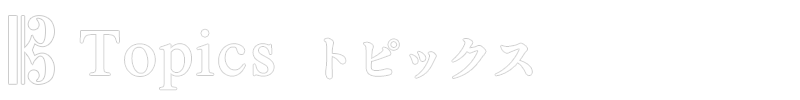
 クラシック・リスナーに贈る
クラシック・リスナーに贈る