ジャズに限らず「オールスター夢の共演」という企画は心躍るもの。ふだんは顔を合わせることのない大物たちが一夜限り一堂に会し、一つの音楽を作り上げる光景は、しばしば演奏の成否を超えて聴く者に感動を与えてくれます。
ところが人間というのは欲深いもので、そういう企画が一度成功すると、どうしても2匹目、3匹目のドジョウを狙いたくなるのですね。たとえば、一期一会だったはずのオールスター・グループに名前をつけて定期的にレコーディングやライブをおこなわせる。もちろんメンバーは腕達者揃いですから、演奏すればそれなりの水準にはなります。しかしそれゆえに音楽が、工夫もスリルもない“抜け殻”になってしまいがちなのも否めない事実。もともとジャズというのは一回性を重視した――裏を返せば一丁上がり!的要素の強い音楽です。だからこそプロデューサーも演奏者自身も、手を変え品を変え表現の鮮度を保とうとするわけですが、そういう観点からいくとこの「オールスター・グループの恒常化」というのは、ジャズ本来の在りようとは矛盾する行為なのかもしれません。
しかし中には、オールスター的でありながら、その音楽のハイクオリティを保ち続けるユニットもあります。今回ご紹介するThe L.A.4もその一つです。
 L.A.4は1974年、当時のアメリカ西海岸を代表するジャズマン4人が集まり結成されたユニットです。アルト・サックスのバド・シャンクは、そのクール&インテリジェントなブロウ・スタイルで、チェット・ベイカーやジェリー・マリガンとともにウェストコースト・ジャズの全盛期を彩ったスター・プレイヤー。またドラムのシェリー・マンも、モダン・ジャズの黎明期から多くのセッションに参加し、繊細さと大胆さを併せ持ったパフォーマンスで白人ジャズマンの地位向上に大きく貢献した大立て者です。そしてベースのレイ・ブラウンは東西海岸を股にかけその名をとどろかせた斯界の第一人者。堅実でありながら懐の深い彼のプレイは、まさにジャズ・ベース最良のモデルといっても過言ではないでしょう。
しかしそれにも増して重要なのが、ギタリスト、ローリンド・アルメイダの存在です。そもそもL.A.4結成のきっかけは、彼とシャンクが50年代に組んでいた双頭グループのリユニオンだったのですが、そういう事情を差し引いても、彼のこのユニットにおける音楽的ウェイトの重さは計り知れません。ブラジル出身ならではの躍動とサウダージ。カンファタブルなスイング感とハーモニー・ワーク。リスナー・フレンドリーな音楽性。……知名度という点では先の3人に一歩譲るアルメイダですが、もしこの人がいなかったらL.A.4がこれほどの独自性を持つことはできなかっただろうと僕には思えます。
 では、そんな4人が集まって生み出されるのはどういう音楽か。ひと言でいうなら、それは、「エレガントなラテン・テイストを伴った室内楽的ジャズ」ということになるでしょう。ウェストコースト・ジャズの持ち味である趣味の良いアレンジと、洗練の極みともいうべきインタープレイから成るその音楽は、あるいはジャズに崇高な精神性やエモーションの発露、濃厚なブルース・フィーリングを求める人には物足りなく感じられるかもしれません。しかしだからといってL.A.4のジャズが音楽的な野心や誠実さに欠けるわけではまったくなく、それどころか、意匠を凝らし、技術の粋を尽くしながら、誰もが楽しめるジャズを作り出そうとするその態度には、オールスター・グループにはあるまじき(笑)真摯ささえ感じられます。 では、そんな4人が集まって生み出されるのはどういう音楽か。ひと言でいうなら、それは、「エレガントなラテン・テイストを伴った室内楽的ジャズ」ということになるでしょう。ウェストコースト・ジャズの持ち味である趣味の良いアレンジと、洗練の極みともいうべきインタープレイから成るその音楽は、あるいはジャズに崇高な精神性やエモーションの発露、濃厚なブルース・フィーリングを求める人には物足りなく感じられるかもしれません。しかしだからといってL.A.4のジャズが音楽的な野心や誠実さに欠けるわけではまったくなく、それどころか、意匠を凝らし、技術の粋を尽くしながら、誰もが楽しめるジャズを作り出そうとするその態度には、オールスター・グループにはあるまじき(笑)真摯ささえ感じられます。
この「なき王女のためのパヴァーヌ」は、そんな彼らの音楽性が端的に示された名盤です。取り上げられている曲はボサノバを含むスタンダードがほとんどで、一見すると「またかよ……」という印象も受けるのですが、聴いてみればそこにはマンネリ感やおざなり感は一切なし。かといってそれは鬼面人を驚かすような演奏でも全然ないのです。一つだけ例を挙げると、ラヴェルの書いたアルバム・タイトル曲。中間部、アルメイダのスタティックなテーマの提示と、それに続いてあらわれるシャンクのジャジーな一吹きは、まさにこのグループのコンセプトを象徴する景色といえるでしょう。
初夏の一夕、L.A.4が運んでくれる西海岸の音に身をゆだねてみてはいかがですか?
|

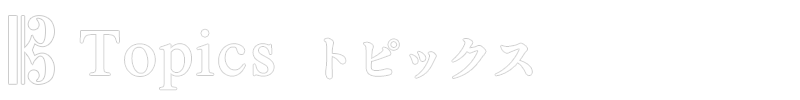
 クラシック・リスナーに贈る
クラシック・リスナーに贈る 「なき王女のためのパヴァーヌ」The L.A.4
「なき王女のためのパヴァーヌ」The L.A.4