みなさんがこの号を手に取られる頃はもう終わっているかもしれませんが……「あまちゃん」、おもしろかったですね。僕も毎朝その日最初の放送を観て、1日を乗り切るエネルギーを充電させてもらっていました。音楽もよかった。特にオープニング・テーマ! 担当した大友良英さんは「半年間飽きずにきいてもらえるみそ汁のような曲をめざした」とおっしゃっていますが、いやいやいや、飽きるどころか、このテーマ曲を含むサントラ盤は、朝ドラとしては初のオリコン・トップ10入りという異例の大ヒットとなったそうです。
それにしてもこの音楽、どうしてこんなに人を惹きつけるのか。それは――もちろんドラマとの相乗効果ということもあるでしょうが――これが、演奏者の表現の初発性、平たくいえば「演って楽しい!」という気持ちを最優先して作られているからではないでしょうか。きけば大友さんは、すべてを自分の中で完結させるのではなく、多くの部分を演奏者の裁量に任せて音楽を仕上げていったのだとか。この話をきいた時、僕は「そういえばあの人もこういう音楽をやってるなぁ」とあるミュージシャンのことを思い出しました。それが今回ご紹介するカーラ・ブレイです。
 カーラ・ブレイは1960年代半ばから活躍している女流作曲家兼バンドリーダー兼キーボード奏者です。父親は教会のオルガニスト。当然幼い頃から音楽は生活の一部として身近にありましたが、しかし彼女、お父さんから基礎的な手ほどきを受けた以外には、アカデミックな音楽教育を受けたことは一切なかったそうです。けれどそのことが幸いしたのでしょう。長じてカーラは、狭いジャズの慣習から解放された、独創性と本質性を兼ね備えた音楽を書き、演奏するようになり、時にはデューク・エリントンやギル・エヴァンスと並び称されるほどの存在となるのです。 カーラ・ブレイは1960年代半ばから活躍している女流作曲家兼バンドリーダー兼キーボード奏者です。父親は教会のオルガニスト。当然幼い頃から音楽は生活の一部として身近にありましたが、しかし彼女、お父さんから基礎的な手ほどきを受けた以外には、アカデミックな音楽教育を受けたことは一切なかったそうです。けれどそのことが幸いしたのでしょう。長じてカーラは、狭いジャズの慣習から解放された、独創性と本質性を兼ね備えた音楽を書き、演奏するようになり、時にはデューク・エリントンやギル・エヴァンスと並び称されるほどの存在となるのです。
中でも彼女の名をジャズ史に深く刻み込んだ出来事が、1965年のJCOA(ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ・アソシエーション)の設立です。これは、ジャズ・ミュージシャン(特に不遇を託っていたフリー・ジャズ系のミュージシャン)の権利を自分たちの手で保護することを目的とした団体で、その後フリー・ジャズ・ムーヴメントの大きな牽引力となっていき、そのリーダーの1人だったカーラは「フリー・ジャズの女帝」などと呼ばれたものでした。
こうやって書くと「なんかコワそうな革命の女闘士」という印象を持たれてしまうかもしれませんし、事実彼女にはそういう側面もなくはないのですが、しかし彼女の生み出す音楽それ自体は、難解なところなど微塵もない、ユーモラスで、叙情的で、躍動的で、自由闊達なものばかりです。さらにそこには、幼い頃から父親の傍らで親しんできた賛美歌的テイストもふんだんに盛り込まれており、聴く者の心を安寧の世界に連れていってくれもします。そう、彼女にとってフリーでなくてはならないのは、形式ではなく、「音楽に対する精神」なのです。

そんな自由な音楽観を反映してか、カーラにはデュオからオーケストラまで多彩なフォーマットの作品があり、そのどれもが高い完成度を有しているため1枚を選ぶのがむずかしいのですが、ここでは名盤の誉れ高い「ライヴ!」をご紹介することにしましょう。
このアルバムを聴いてまず耳を捉えるのは、その奔放さ、そして率直さです。ここに参加しているメンバーは、皆百戦錬磨の手練ればかりで、その気になれば一糸乱れぬ精密なアンサンブルも容易くやってのけることができるはずなのですが、カーラは彼らにそんなことは望みません。たとえば1曲目の≪ブラント・オブジェクト≫。ファンキーな16ビートの、表向きは当時流行していたフュージョン・フィギュアを持ったこの曲を、しかし彼らは、精緻さよりも自然発生的なグルーヴに重きをおいて演奏します。結果その音楽は、量産的なフュージョンではあり得ない強烈なエネルギーを発散することとなるのです。あるいは≪タイム・アンド・アス≫。ポップな曲想の陰に見え隠れする甘やかな毒は、彼女の音楽家としての矜恃のあらわれであるように僕には思えます。
しかしながら本作中の白眉は、なんといっても≪ハレルヤ!≫でしょう。賛美歌的シンプルさとブルージーな哀感が渾然一体となったこの曲/演奏は、まさにカーラの音楽の核心と呼び得るもの。あまちゃんにシビれた人なら、うれしい驚きのあまり思わず「じぇじぇじぇ!」と叫んでしまうに違いありません。 |
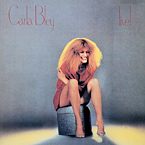

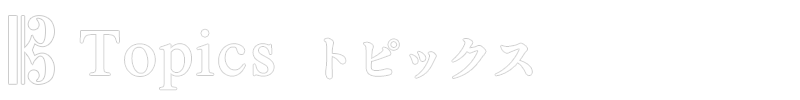
 クラシック・リスナーに贈る
クラシック・リスナーに贈る